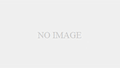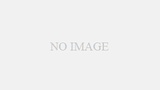長時間残業がもたらす社員や会社への悪影響
長時間に及ぶ残業が社員や会社にどのような影響を与えるのかをWe Are Mammothというサイトが公開しています。
長時間労働や残業が社員や企業にもたらす弊害とは?
https://wearemammoth.com/2013/11/long-hours
クライアントや上司に過度の期待をもたせる
長時間働いた仕事の成果を見たクライアントや上司は「社員は常時これくらいできる」と勘違いしてしまい、その後の業務に支障が出る恐れがあります。
長時間労働を許可する企業は雇用や評判に問題を抱えてしまう
1週間に80~100時間の労働は、社員の健康や精神に悪影響を与えてしまい、長続きせずに退職する人を生み出す原因になります。また、長時間労働を社員に強いている企業の評判は悪く、新しい人材を確保するのにも問題が発生し、結果的に企業は自分で自分の首を絞めることに。
長時間労働はリーダーシップのなさの表れ
長時間労働してまでデッドラインを守るということは、プロジェクトリーダーがクライアントに「製品の納期について賛成できません」と強く言えない、ということになり、クライアントと対等な関係を築けていないことを意味します。
プロジェクトマネージメントがうまくいっていない時に長時間労働が発生
納期までに仕事を終わらせるため週末や遅くまでの残業が必要になるということは、プロジェクトリーダーが、チームメンバーに対する配慮のなさ・時間配分ミスなどの問題を抱えていることの印です。
残業は生活リズムを狂わせる
残業をすればするほど、仕事後にするべきであった家族サービス・食事・家事・睡眠・趣味などに費やす時間がなくなり、生活リズムが狂ってしまいます。
長時間労働が会社への信仰心を育てる
「昨日仕事を終えて帰宅したのは22時でしたよ」などと残業を自慢する人は、他人より長時間働くことで自尊心を満たし、自分の評価が上がると勘違いしています。長時間労働は、労働者としての価値を計る物差しにはなりません。
長時間労働では生産性を上げられない
1週間に80時間働いても、週に40時間しか働いてない場合と比べて生産性が上がるわけではなく、反対に長時間働くことでストレスがたまり、集中力は落ちてクリエイティブなアイデアを生み出すのに時間がかかることも。その結果、仕事を早く終わらせることが目標になってしまい、仕事の中身が伴わなくても妥協してしまいます。
長時間労働が日本をダメにした、悪しき労働慣行を壊す時期
長時間残業がもたらす影響は上記の様になっており、長時間残業がいかに無駄かが書かれています。
日本のブラック企業は、ここに残業代なしのサービス残業による弊害も加わりますので更に非効率ですね。
カルビーの松本晃会長がインタビューで長時間労働が日本をダメにした、悪しき労働慣行の壊す時期と提言しています。
カルビー会長が喝!長時間労働が日本をダメにしてきた
https://diamond.jp/articles/-/83598
京都大学から伊藤忠商事へ、ジョンソンエンドジョンソン日本法人社長などを経て、2009年に現職に就任した松本晃会長。
低迷していたカルビーを徐々に上昇させた松本晃会長ですが、昔と現在では状況が異なっており、ビジネスモデルが変化したのであれば労働環境も変化しなければなりませんと述べています。
勿論カルビーでは残業をしない様に早く帰る事を推奨しており、評価制度にはコミットメント&アカウンタビリティを導入している。
カルビーの様に残業が少ない企業への転職は以下のページを参考にして下さい。
長時間労働したからと言って成果が出るとは限りません、だったら早く帰って家族や友人と一緒に過ごして次に繋げた方が良いと言うのは当然の事なのですが、それが出来ないのですよね。
残業が多い理由は経営者
経営者がリスクも責任も取らない事は会社員で有ればご存知だと思いますが、経営者だけでなく周囲の目も気になる事が残業が多くなる原因でも有りますよね。
上司や先輩よりも先に帰ってはならないと言う習慣が根付いており、残業の多さが評価されると言う企業も未だに多く存在します。残業手当にも言及していますが、残業手当すら出ないブラック企業も有る。更に残業は減らすが出勤日数を増やす悪質な企業も見かけます。
こんな事が続いていては誰も働きたく無くなり、結果として収入が減り、少子晩婚化、そして人口減少の人手不足と言う連鎖となりました。
長時間の残業をしなければ生き残れない企業は、既にビジネスモデルが破綻している事を認識した方が良いでしょう。
36協定の弊害と高度プロフェッショナル制度
長時間労働については36協定によって合法化となっており、36協定を知っている人も多いですね。
しかしながら36協定を締結したとしても、残業代を支払わないサービス残業となると話は別です。
36協定は長時間の残業を許容するが時間外の残業代はモチロン支払わなければなりませんし、深夜であれば割増率は高くならなければなりません。
36協定を締結するには労組もしくは過半数代表者と労使交渉で合意する必要があり、勝手に適用される訳ではありません。
何か勘違いしている経営者が多いですが、従業員もよく理解していない事が多いです。
36協定だからと言われ、はいそうですかで終わってしまう事が36協定の弊害でしょう。
名ばかり管理職でサービス残業を許容するホワイトカラーエグゼンプションも一般的に知られる様になりましたが、特定業種の特定職種かつ高年収の労働者を対象として高度プロフェッショナル制度として施行されています。
高プロ制度はホワイトカラーエグゼンプションとは異なり、適用対象者が非常に限定されていますので、高プロ適用者の割合は1%前後です。
社員も高プロ適用されそうになったら辞めて転職してしまう事もあり、企業側も適用しない事が多くなっています。
36協定と高プロを理解する事で無駄に疲弊する事もなくなるでしょう。